「高分子の溶解度は小さい」というのは高校の時に習う話ですが、その理由を知っている人は少ないと思います。
この記事では、高分子が溶けにくい理由をフローリー・ハギンズモデルを用いて解説します。
高分子が溶けにくい理由
溶けやすさとギブス自由エネルギーの関係
高分子の溶解は、ギブズ自由エネルギー変化 \(\Delta G\)で表されます。
\(\large{\Delta G = \Delta H – T \Delta S}\)
ここで、
- \(\Delta H\) :エンタルピー変化(溶媒-高分子間の相互作用の影響)
- \(\Delta S\) :エントロピー変化(溶解時の乱雑さの増大)
高いところから物が落ちるのと同様、エネルギーが低くなるように物事は進むため、溶解が進むためには、\(\Delta G < 0\)である必要があります。
しかし、高分子の場合、低分子の時よりエントロピー変化 \(\Delta S\) が小さくなってしまいます。特に、分子量が大きくなるほど \(\Delta S\) の寄与が減少し、溶解が困難になります。
この理由をフローリー・ハギンズモデルを用いて説明します。
フローリー・ハギンズモデル
フローリー・ハギンズモデルとは、下の図のようなモデルです。
◯:溶媒分子、●:高分子セグメントというようになっています。

ここで、このモデルを考えるうえで、
- 溶媒分子と高分子セグメントの体積は等しい
- 個々の高分子セグメントは平均濃度の環境中にある(平均場近似)
という2つの仮定を導入しています。
さて、上の図を見ると分かる通り、高分子溶液では低分子の場合と違って高分子セグメントがつながっている分、溶質分子が拡散しにくくなっていることが分かります。
したがって、高分子は低分子よりも溶解したときに増えるエントロピーが少なくなり、その結果ギブス自由エネルギーが負になりにくいため、溶けにくいのです。
なお、高分子同士の混合はさらに獲得エントロピーが減るので、ほぼ起こりません。
(参考)高分子と溶媒の相互作用(溶媒との親和性)
高分子が溶解するには、高分子-溶媒間の相互作用が、高分子同士の相互作用より強くなければなりません。
溶媒は、3つの種類に分けられます。
- 良溶媒(good solvent):高分子と溶媒の相互作用が強く、分子鎖が溶媒中に広がる(例:水中のポリビニルアルコール)
- θ溶媒(theta solvent):高分子同士の相互作用と溶媒との相互作用が釣り合い、理想鎖のようにふるまう(例:特定温度のシクロヘキサン中のポリスチレン)
- 貧溶媒(poor solvent):溶媒との相互作用が弱く、高分子同士が凝集しやすくなる(例:水中のポリスチレン)
溶媒が高分子と適切な相互作用を持たない場合、高分子鎖が広がることができず、沈殿やゲル化が起こります。
特に、疎水性の高い高分子(ポリエチレン、ポリプロピレンなど)は、水のような極性溶媒にはほとんど溶けません。これは、水分子間の水素結合が強く、疎水性の高分子と相互作用しにくいためです。
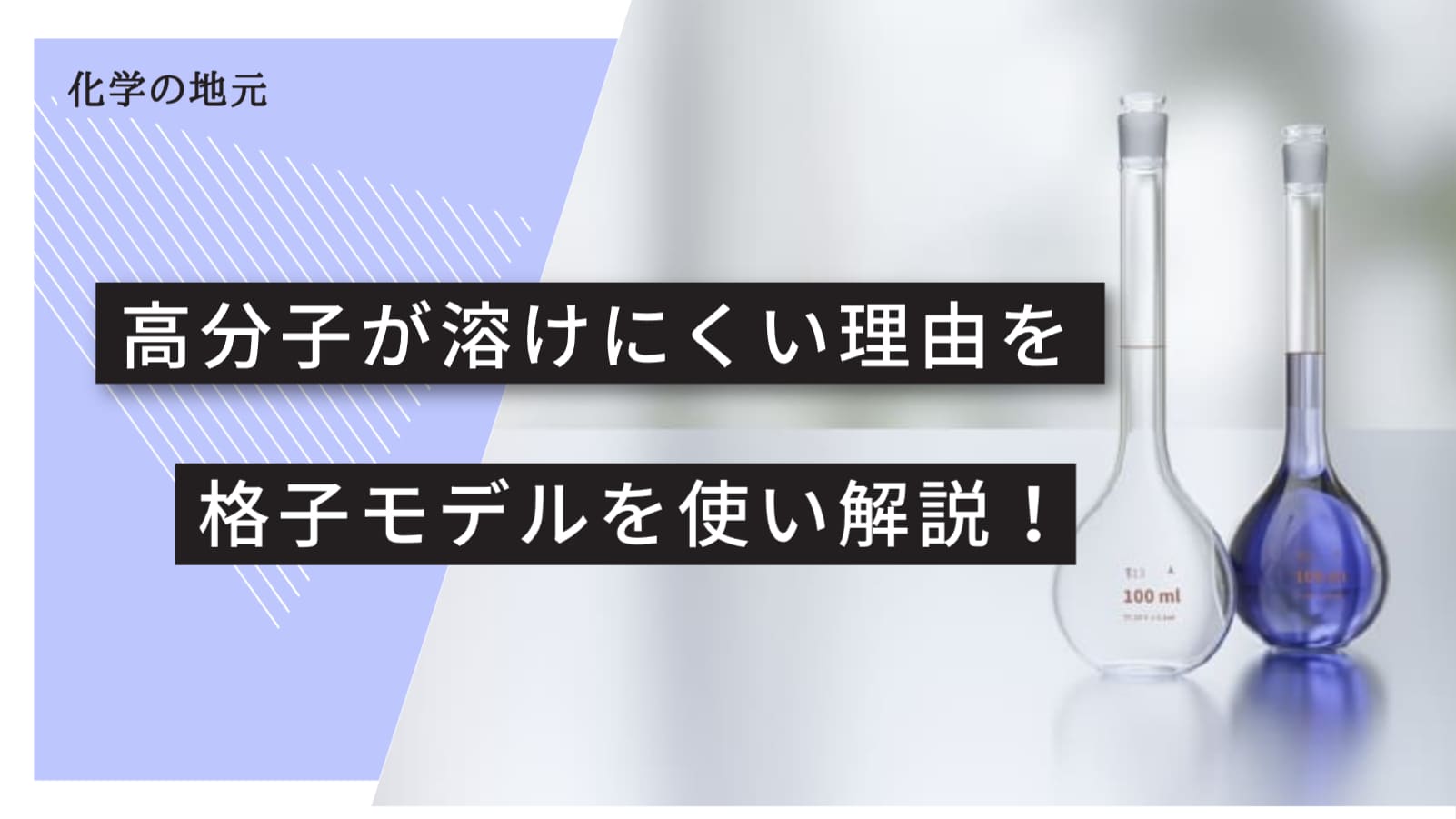
コメント