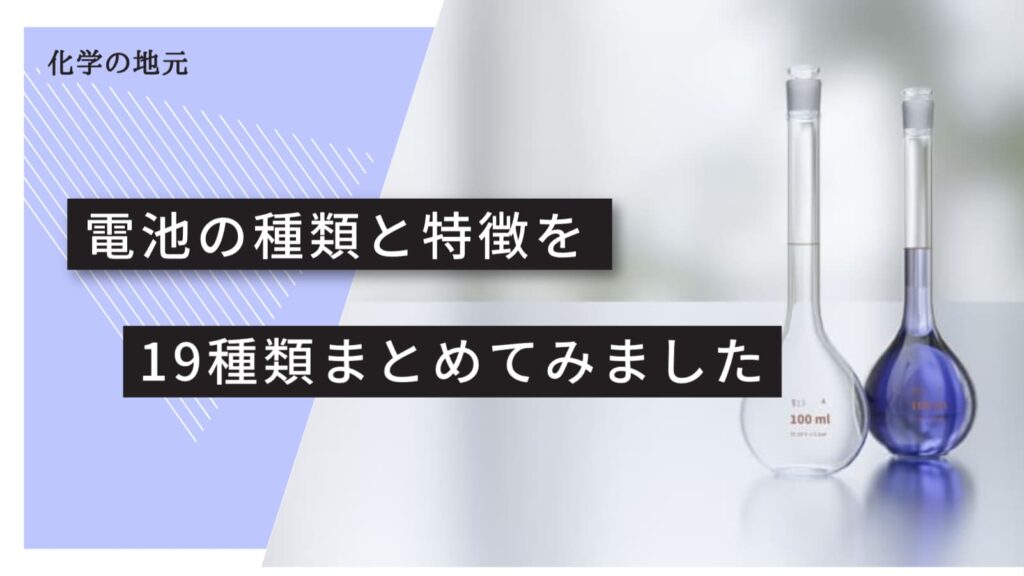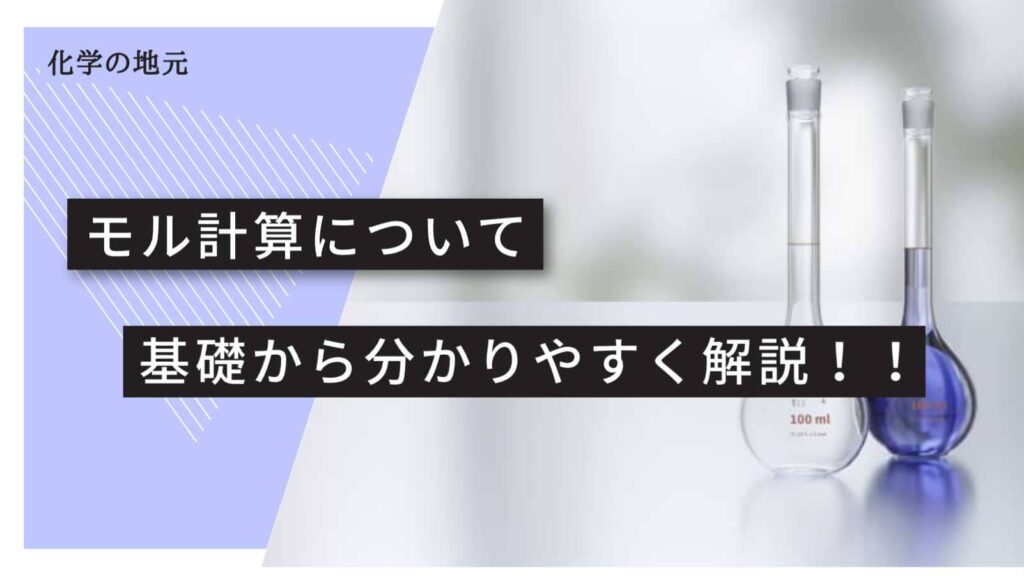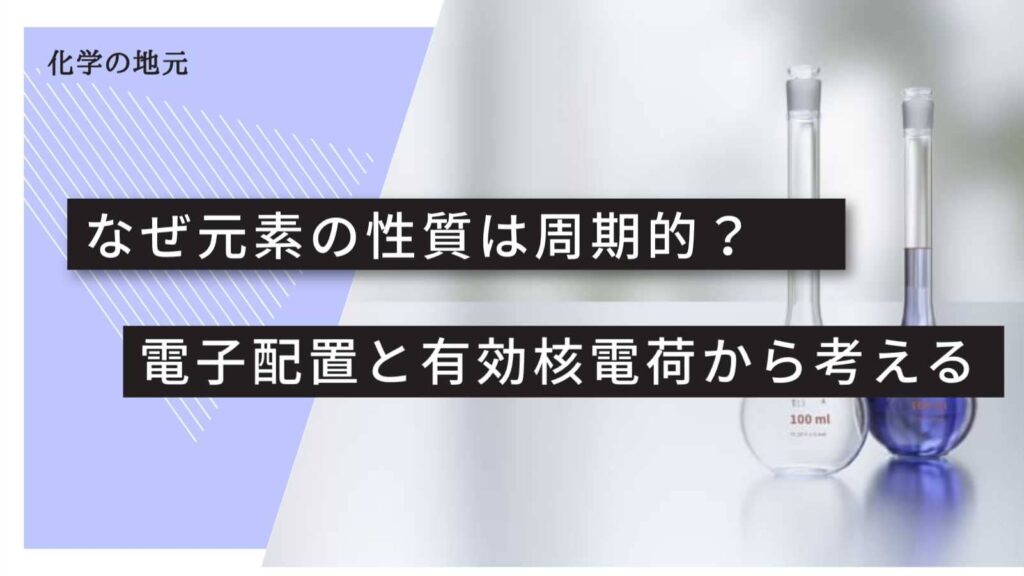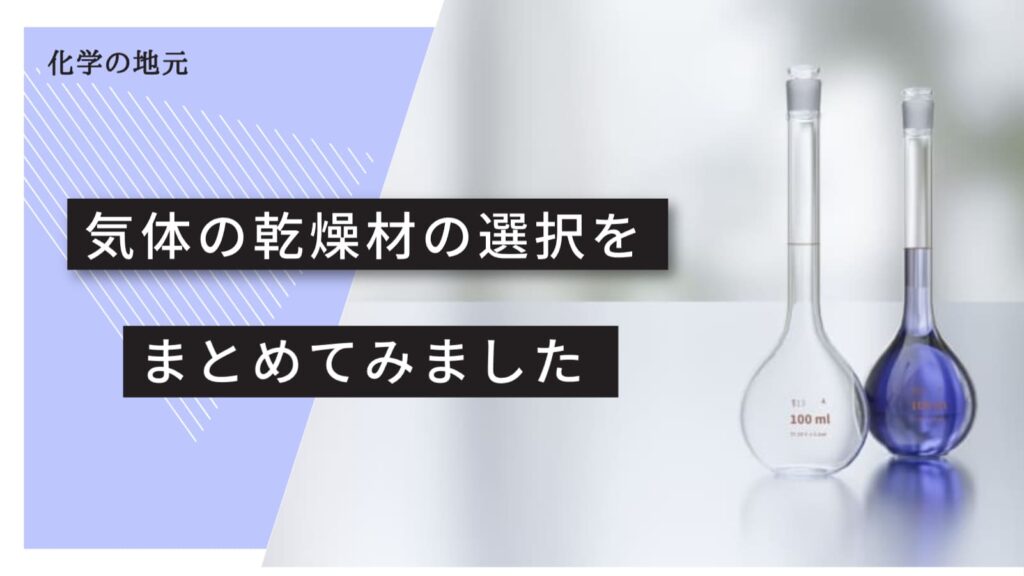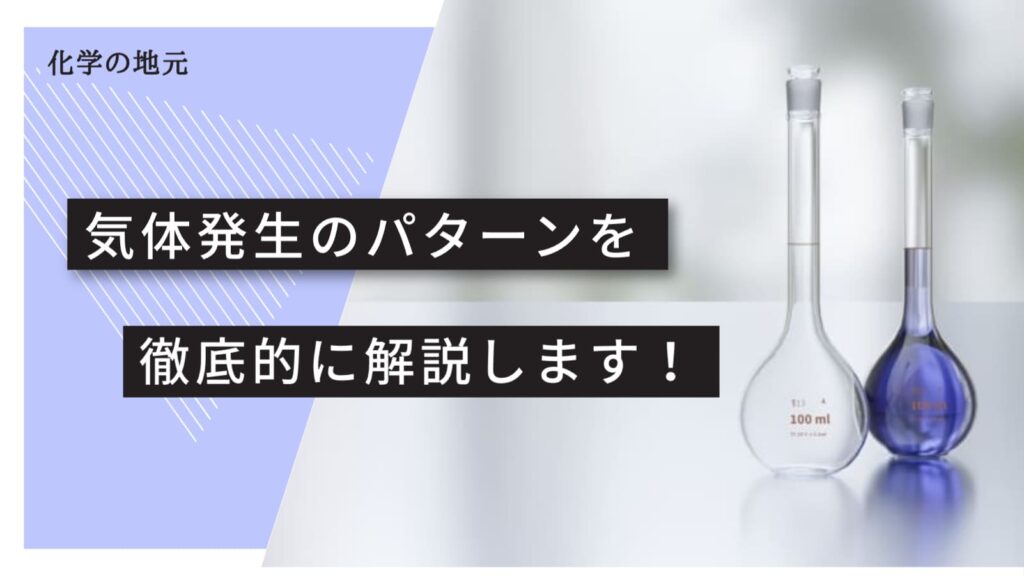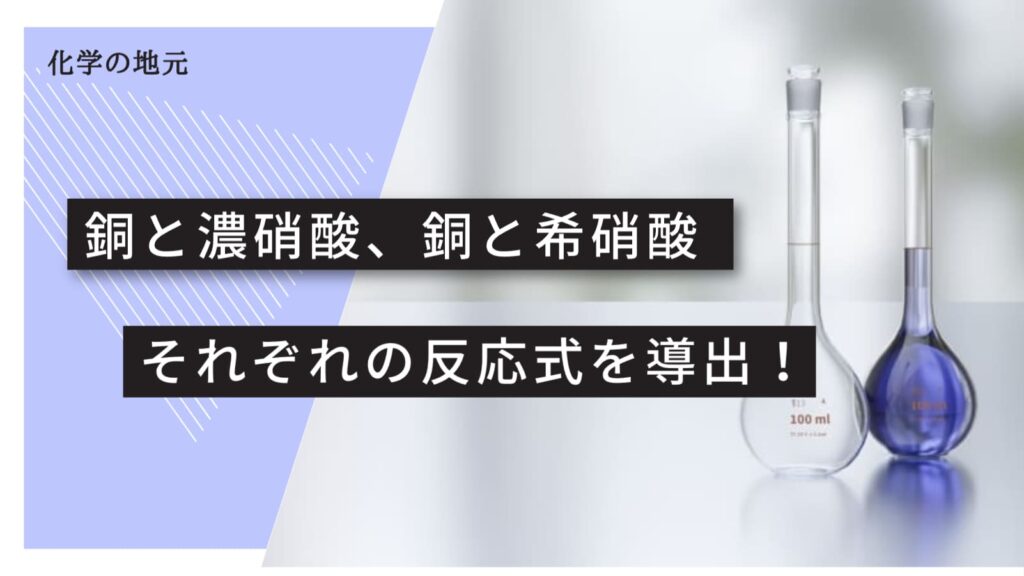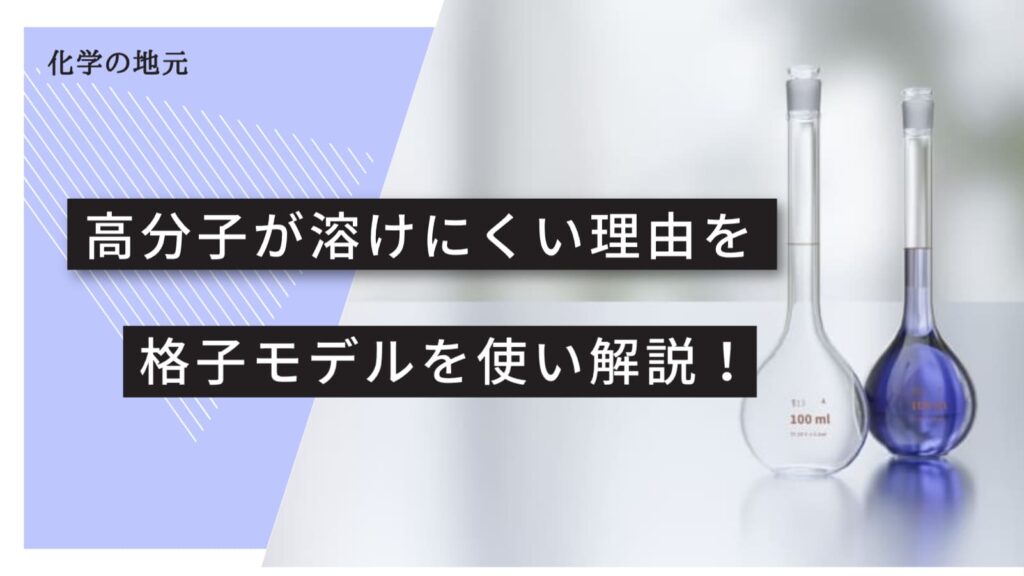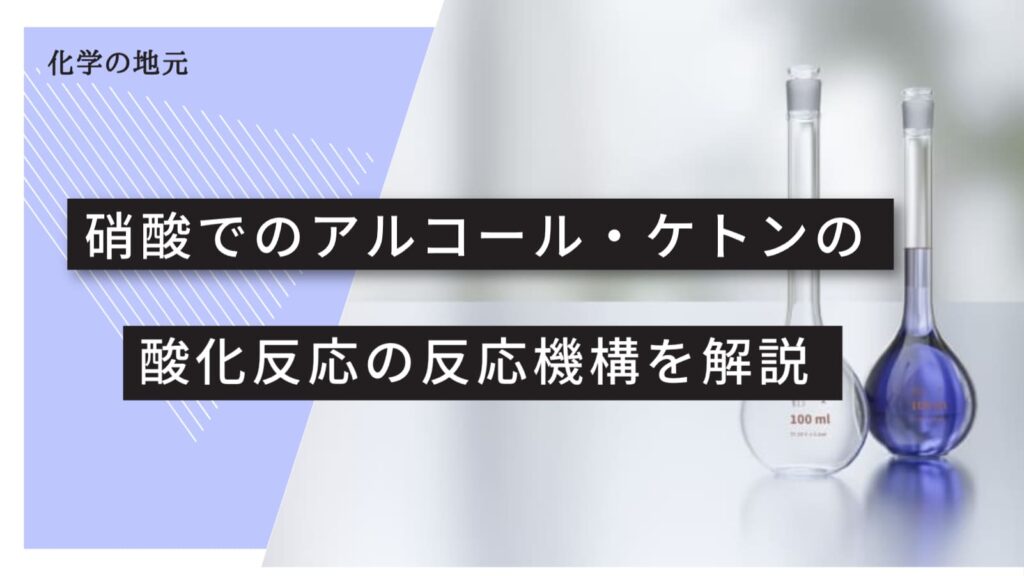-

知ればもっと美味しくなる!料理の科学~味と食感を変える魔法の正体~
いつもの料理が、ちょっとした工夫で劇的に美味しくなる。それはまるで魔法のようですが、実は科学の力なんです!加熱、冷却、混ぜる…といった調理の過程で、食材の中では様々な化学反応が起きています。今回は、料理の味や食感に大きな影響を与える代表的... -

電池の種類と特徴を19種類まとめてみました
各種電池の反応と特徴 以下に、ご提示いただいた各種電池の正極反応と負極反応、そして特徴をまとめました。 1. ダニエル電池 正極反応: $\ce{Cu^{2+}(aq) + 2e^- -> Cu(s)}$ 負極反応: $\ce{Zn(s) -> Zn^{2+}(aq) + 2e^-}$ 特徴: 持続的に安定した電流を... -

【化学の超基本】「モル(mol)」って何?苦手な人も今日からスッキリ理解!
「モル(mol)」という言葉、化学の授業で必ず出てきますよね。「なんだか数が大きくて、よく分からない…」と感じている人もいるかもしれません。でも大丈夫!この記事を読めば、モルの概念がスッキリと理解できるようになりますよ。一緒にモルの世界を見... -

なぜ元素の性質は周期的?電子配置と有効核電荷で解き明かす周期表の謎
「なぜ周期表の元素たちは、あんな風に綺麗に性質が変化していくのだろう?」 理科の授業で周期表に触れたとき、誰もが一度は抱く疑問ではないでしょうか。金属元素が並ぶエリア、気体になる元素が集まるエリア、そして反応性に富んだハロゲンや、安定な貴... -

【これで完璧!】IUPAC命名法マスターへの道 ~優先順位も徹底解説&練習問題~
1. はじめに:なぜIUPAC命名法が重要なのか? 有機化学を学ぶ上で欠かせないのが、化合物の名前の付け方、IUPAC命名法です。これは「化学の世界共通言語」とも言える国際的なルール。これがなければ、同じ化合物でも呼び方がバラバラになり、化学の世界は... -

気体の乾燥剤を全て解説【酸性・中性・塩基性】
気体を乾燥させるためには、その性質に適した乾燥剤を選ぶ必要があります。乾燥剤の選択を間違えると、気体が乾燥剤と反応してしまうため注意が必要です。本記事では、乾燥剤の種類と、それぞれに適した気体の選び方について解説します。 代表的な乾燥剤と... -

【高校化学】気体発生のパターンを徹底解説
化学実験や試験問題では、特定の反応から気体が発生するパターンを理解することが重要です。本記事では、気体が発生する代表的なパターンと具体例をまとめます。 気体発生のパターン まず、気体発生のパターンを大まかに7つに分類します。 発生方法加熱の... -

銅と希硝酸、濃硝酸の反応の反応式の導出
銅(Cu)は酸化力の強い酸と反応しますが、酸の濃度によって反応が異なります。ここでは、希硝酸と濃硝酸の場合の化学反応式を導出する方法を説明します。 銅と希硝酸の反応 (1) 反応の概要 希硝酸(\(\ce{HNO3}\))は酸化力が弱いため、銅を溶かすには還... -

高分子が溶けにくい理由はエントロピーにある
「高分子の溶解度は小さい」というのは高校の時に習う話ですが、その理由を知っている人は少ないと思います。 この記事では、高分子が溶けにくい理由をフローリー・ハギンズモデルを用いて解説します。 高分子が溶けにくい理由 溶けやすさとギブス自由エネ... -

アルコール・ケトンの硝酸による酸化の反応機構を解説!
硝酸が酸化剤として用いられることは高校でも習いますが、その反応機構までは習いません。 この記事ではその反応機構を解説します。 硝酸の反応機構 実際のステップ ヒドロキシ基(アルコール) STEP硝酸の窒素がヒドロキシ基の酸素に求電子攻撃 硝酸の窒...