「ギブスエネルギーって何?」「ΔG って教科書でよく見るけど、いまいちピンとこない…」 大学で化学を学び始めると、特につまずきやすい概念の一つが ギブスエネルギー (Gibbs energy) ではないでしょうか?
しかし、ギブスエネルギーは化学反応が自発的に進むのか、それとも進まないのかを判断するための非常に強力なツールです。この概念を理解することで、化学平衡や電池の起電力など、様々な化学現象の理解が一気に深まります。
この記事では、
- ギブスエネルギーの定義と物理的な意味
- ギブスエネルギー変化 (ΔG) と反応の自発性の関係
- 標準ギブスエネルギー変化 (ΔG∘) とは?
- ギブスエネルギーと平衡定数の関係
- ギブスエネルギーの具体的な活用例
などについて、数式だけでなく言葉や図も用いて、できるだけ分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、ギブスエネルギーの本質を理解し、化学の学びがさらに面白くなるはずです。
ギブスエネルギー(G)とは? – 定義と物理的な意味
ギブスエネルギー(記号:G)は、19世紀にアメリカの物理学者ジョサイア・ウィラード・ギブスによって導入された熱力学的な状態関数です。その定義は以下の式で与えられます。
\(\large{G=H−TS}\)
ここで、
- H:エンタルピー (Enthalpy) – 物質が持つエネルギーの一種で、内部エネルギー U と圧力 P、体積 V の積の和 (H=U+PV) で表されます。大まかには「物質が蓄えている熱量」のようなイメージです。
- T:絶対温度 (Absolute temperature) – ケルビン(K)を単位とする温度です。
- S:エントロピー (Entropy) – 物質や系の「乱雑さ」や「無秩序さ」の度合いを表す尺度です。
ギブスエネルギーは、一定温度 (T)・一定圧力 (P) の条件下で、系が外部に行うことができる最大の「非膨張仕事」を表します。 「非膨張仕事」とは、体積変化以外の仕事のことで、例えば電池における電気的な仕事などがこれに当たります。
なぜギブスエネルギーが必要なのか?
化学反応が自発的に進むかどうかを判断する際に、エンタルピー変化 (ΔH) だけでは不十分です。例えば、吸熱反応 (ΔH>0) でも自発的に進む反応があります(例:食塩が水に溶ける)。これは、反応系だけでなく周囲も含めた宇宙全体のエントロピー増大という、より普遍的な法則(熱力学第二法則)が関わっているためです。
ギブスエネルギーは、このエンタルピーとエントロピーの両方の効果を一つの指標にまとめたもので、特に化学反応の方向性を議論する上で非常に便利な概念なのです。
ギブスエネルギー変化 (ΔG) と反応の自発性
化学反応において私たちが注目するのは、ギブスエネルギーの値そのものよりも、反応前後でのギブスエネルギー変化 (ΔG) です。一定温度の条件下では、ΔG は以下のように表されます。
\(\large{ΔG=ΔH−TΔS}\)
この ΔG の符号によって、一定温度・一定圧力下での化学反応の自発性を判断できます。
- ΔG<0 (負の値): 反応は自発的に進む(生成物側へ進みやすい)。
- ΔG>0 (正の値): 反応は自発的に進まない(逆反応が自発的に進む)。
- ΔG=0: 反応は平衡状態にある(正反応も逆反応も見た目上進まない)。
なぜ ΔG<0 で自発的に進むのか?
これは、宇宙全体のエントロピー変化 (ΔSuniv) と関連しています。熱力学第二法則によれば、自発的な変化は常に宇宙全体のエントロピーが増大する方向 (ΔSuniv>0) に進みます。 実は、一定温度・一定圧力下におけるギブスエネルギー変化は、
\(\large{ΔG=−TΔS_{univ}}\)
という関係で宇宙全体のエントロピー変化と結びついています。温度 T は常に正の値なので、ΔSuniv>0 (自発変化)であるためには、ΔG<0 となる必要があるのです。
ΔH、ΔS、温度 T と ΔG の関係
ΔG=ΔH−TΔS の式からわかるように、反応の自発性はエンタルピー変化 (ΔH)、エントロピー変化 (ΔS)、そして温度 (T) のバランスによって決まります。
| ΔH の符号 | ΔS の符号 | 低温での ΔG | 高温での ΔG | 自発性 | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | + | – | – | 常に自発的 | 多くの燃焼反応 |
| + | – | + | + | 常に非自発的(逆反応が自発的) | |
| – | – | – | + | 低温で自発的、高温で非自発的 | 水の凝固 (−TΔS 項が正になり、高温では ΔH の負を打ち消す) |
| + | + | + | – | 低温で非自発的、高温で自発的 | 水の蒸発 (ΔH>0 でも、エントロピー増大効果で高温で自発的に) |
4つの条件のΔGとTの関係をグラフで表すと以下のようになります。




例えば、水の蒸発 (H2O(l)→H2O(g)) は吸熱反応 (ΔH>0) ですが、気体になることでエントロピーは増大 (ΔS>0) します。そのため、−TΔS の項は負となり、高温になるほどこの項の寄与が大きくなり、ΔG は負になりやすくなります。これが、高温で水が自発的に蒸発する理由です。
標準ギブスエネルギー変化 (ΔG∘)
化学反応のギブスエネルギー変化を比較・議論する際には、基準となる状態が必要です。それが標準状態です。 通常、標準状態とは、圧力 1 bar (ほぼ 1 atm)、温度は指定された温度(多くの場合 298.15 K = 25 ℃)における純粋な物質の状態を指します。溶液の場合は、通常 1 mol/L の濃度が用いられます。
この標準状態で起こる反応のギブスエネルギー変化を標準ギブスエネルギー変化 (standard Gibbs energy change) といい、ΔG∘ と書きます。
標準生成ギブスエネルギー (ΔfG∘)
特定の化合物 1 mol が、その成分元素の最も安定な単体から標準状態で生成されるときのギブスエネルギー変化を、標準生成ギブスエネルギー (standard Gibbs energy of formation) といい、ΔfG∘ と書きます。単体の最も安定な状態における ΔfG∘ は定義により 0 となります(例:O2(g), C(graphite))。
任意の化学反応の標準ギブスエネルギー変化 (ΔG∘rxn) は、反応に関わる各物質の標準生成ギブスエネルギーを用いて、以下のように計算できます。
ΔG∘rxn=∑npΔfG∘(生成物)−∑nrΔfG∘(反応物)
ここで、np と nr はそれぞれ生成物と反応物の化学量論係数です。
ギブスエネルギーと平衡定数 (K) の関係
ΔG∘ は標準状態での反応の自発性を示しますが、実際の反応は常に標準状態で行われるわけではありません。非標準状態でのギブスエネルギー変化 (ΔG) は、以下の式で与えられます。
\(\large{ΔG=ΔG^∘+RTlnQ}\)
ここで、
- R:気体定数 (8.314 J K⁻¹ mol⁻¹)
- Q:反応商 (reaction quotient) – ある時点での反応物と生成物の濃度(または分圧)の比。平衡状態に達する前の任意の時点での値です。
反応が平衡状態に達すると、見かけ上反応は進行せず、ΔG=0 となります。また、このときの反応商 Q は平衡定数 (equilibrium constant) K に等しくなります。したがって、
0=ΔG∘+RTlnK
これを変形すると、以下の非常に重要な関係式が得られます。
ΔG∘=−RTlnK
または
K=exp(−RTΔG∘)
この式は、標準ギブスエネルギー変化 (ΔG∘) と平衡定数 (K) を結びつけるもので、以下のことを示しています。
- ΔG∘<0 ならば、K>1 となり、平衡は生成物側に大きく偏ります(反応が自発的に進みやすい)。
- ΔG∘>0 ならば、K<1 となり、平衡は反応物側に大きく偏ります(反応が自発的に進みにくい)。
- ΔG∘=0 ならば、K=1 となり、平衡状態では反応物と生成物の量が同程度存在します。
つまり、ΔG∘ の値から、その反応が平衡状態に達したときに、どれだけ生成物が多く存在するのか(あるいは少ないのか)を定量的に知ることができるのです。
ギブスエネルギーの活用例
ギブスエネルギーは、化学の様々な分野で応用されています。
- 化学反応の方向予測: ある条件下で反応が自発的に進むかどうかを予測できます。
- 化学平衡の位置の予測: 平衡定数 K を計算し、平衡時に生成物がどれだけ得られるかを見積もることができます。
- 電池の起電力の計算: 電気化学においては、ギブスエネルギー変化と電池の最大起電力 E の間に ΔG=−nFE (n: 反応に関与する電子のモル数、 F: ファラデー定数)という関係があり、電池の性能評価に利用されます。
- 相転移の予測: 物質の融解や蒸発といった相転移が起こる温度や圧力を予測するのに使われます。
- 生化学におけるエネルギー代謝: 生体内でのATP(アデノシン三リン酸)の加水分解 (ΔG<0) によって放出されるエネルギーが、様々な生命活動の駆動力となっています。
ギブスエネルギーを学ぶ上でのポイント・注意点
- 各項の意味を理解する: G=H−TS や ΔG=ΔH−TΔS といった式を丸暗記するだけでなく、エンタルピー、エントロピー、温度がそれぞれどのような意味を持ち、ギブスエネルギーにどう影響するのかを理解することが重要です。
- ΔG は反応速度については教えてくれない: ΔG は反応が自発的に進む「可能性」や「方向性」を示すものであり、反応が「どれだけ速く進むか(反応速度)」については何も教えてくれません。反応速度は活性化エネルギーなど、別の要因によって決まります。
- 「一定温度・一定圧力下」を意識する: ギブスエネルギーが反応の自発性の指標となるのは、基本的に一定温度・一定圧力の条件下です。条件が異なれば、別の熱力学関数(ヘルムホルツエネルギーなど)を考える必要があります。
まとめ
ギブスエネルギーは、化学反応の自発性や化学平衡を理解するための鍵となる、非常に重要な熱力学的な指標です。
- ギブスエネルギー G は G=H−TS で定義される。
- ギブスエネルギー変化 ΔG=ΔH−TΔS であり、ΔG<0 なら反応は自発的に進む。
- 標準ギブスエネルギー変化 ΔG∘ は、平衡定数 K と ΔG∘=−RTlnK の関係で結びついている。
最初はとっつきにくい概念かもしれませんが、その意味と使い方をマスターすれば、大学化学の様々な場面で役立ち、化学現象に対する理解が格段に深まるでしょう。
この記事が、皆さんのギブスエネルギーへの理解の一助となれば幸いです。さらに学習を深めたい方は、物理化学の教科書で熱力学の章をじっくり読んでみたり、具体的な計算問題に取り組んでみたりすることをおすすめします。
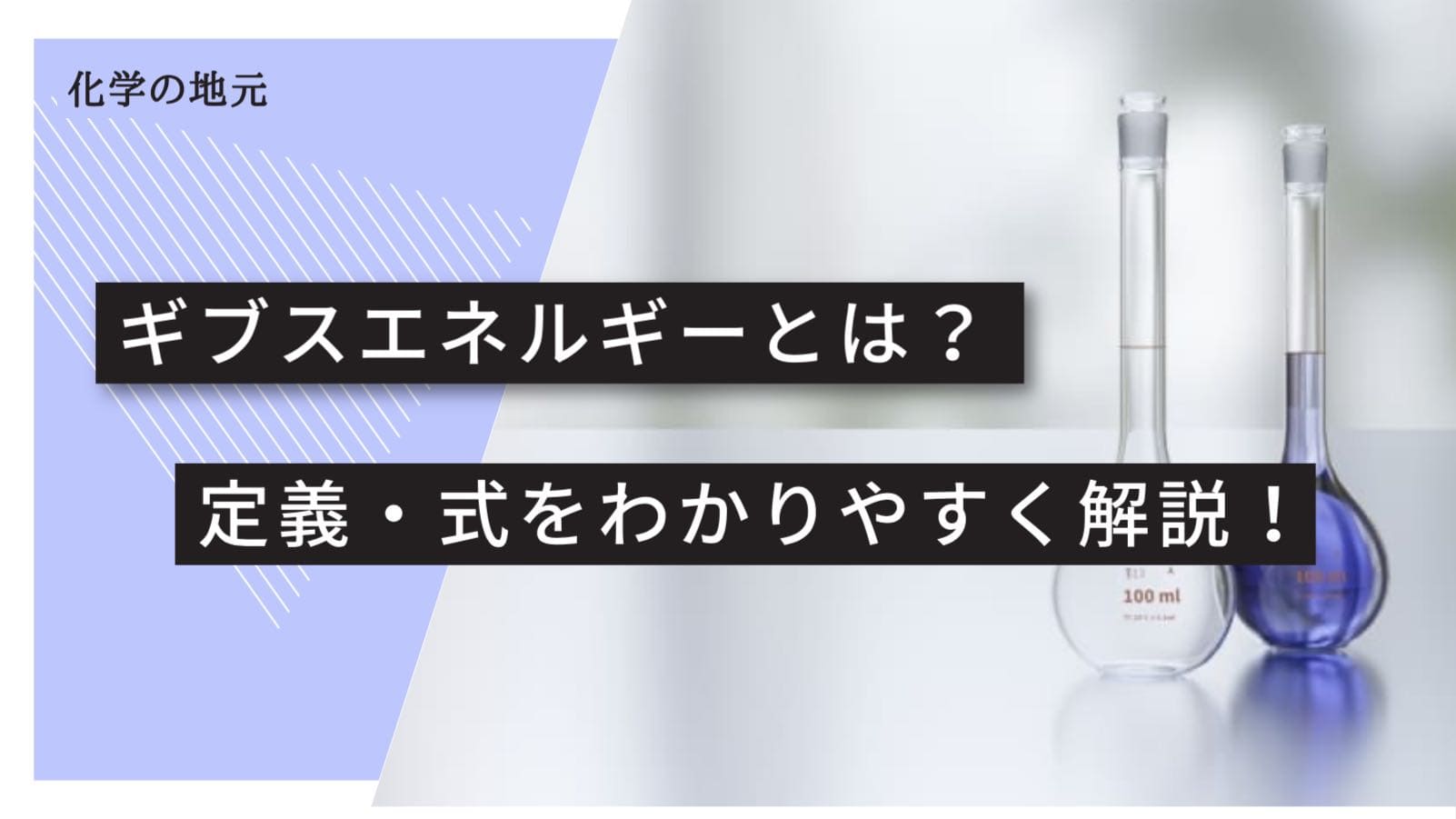
コメント