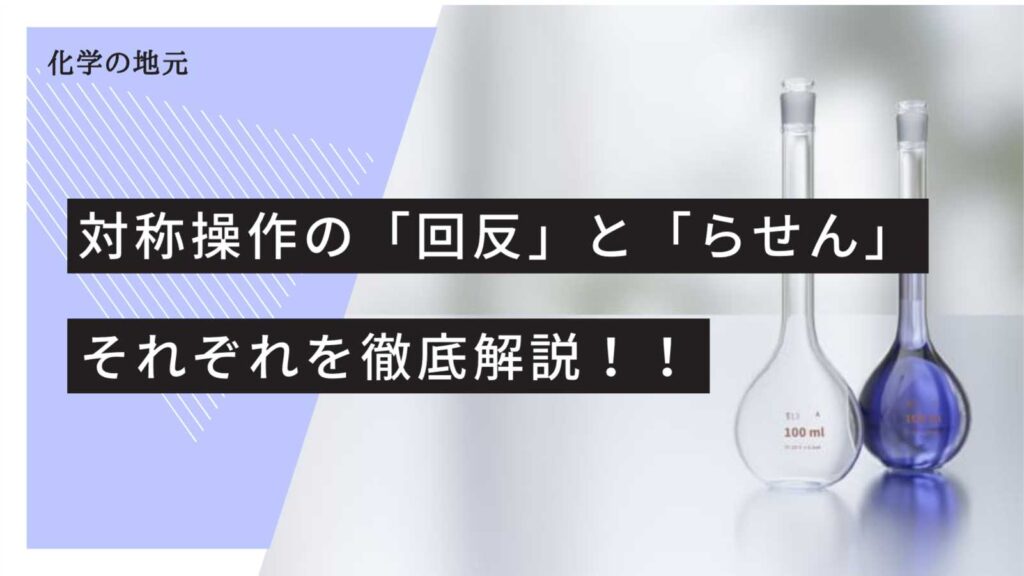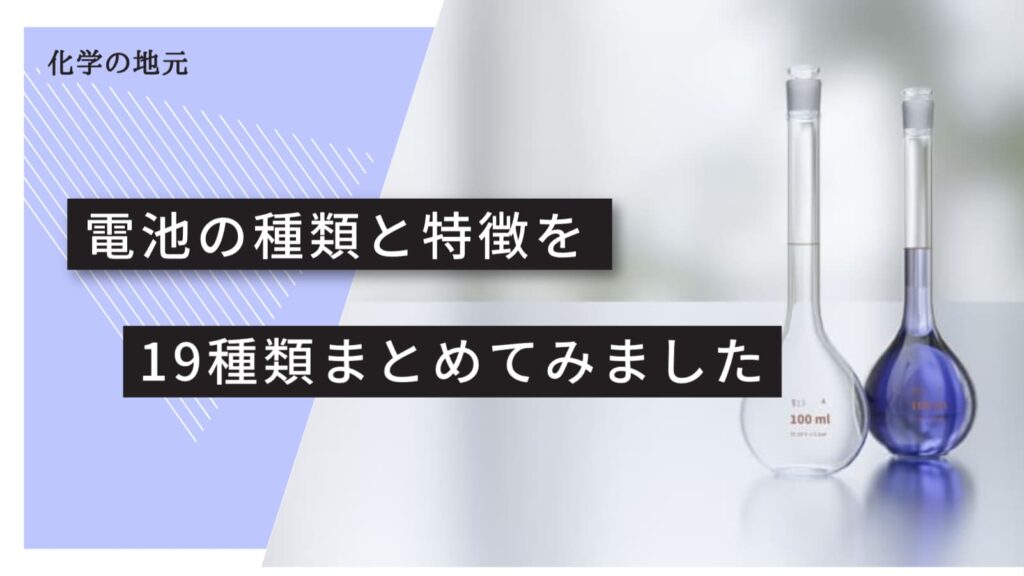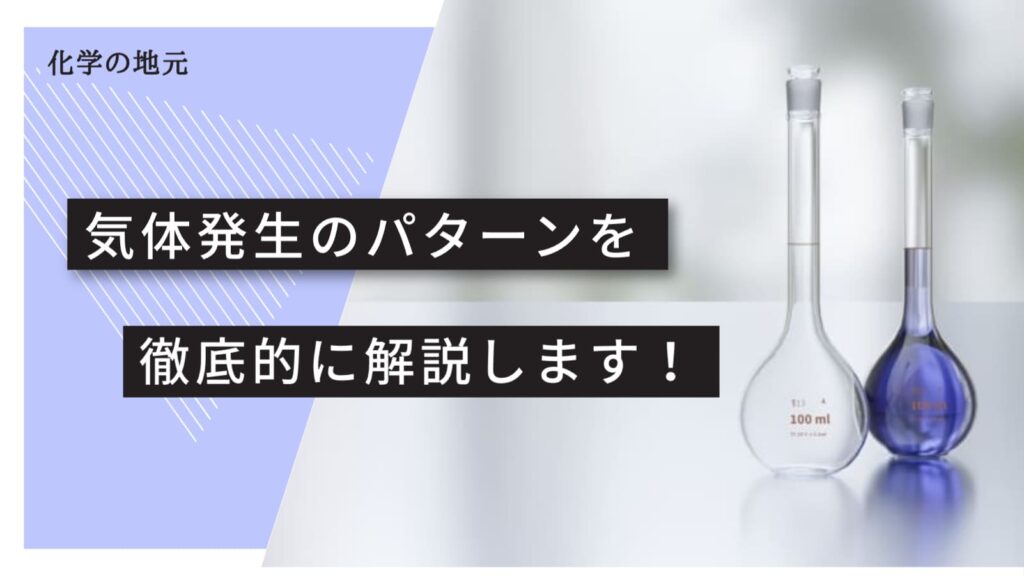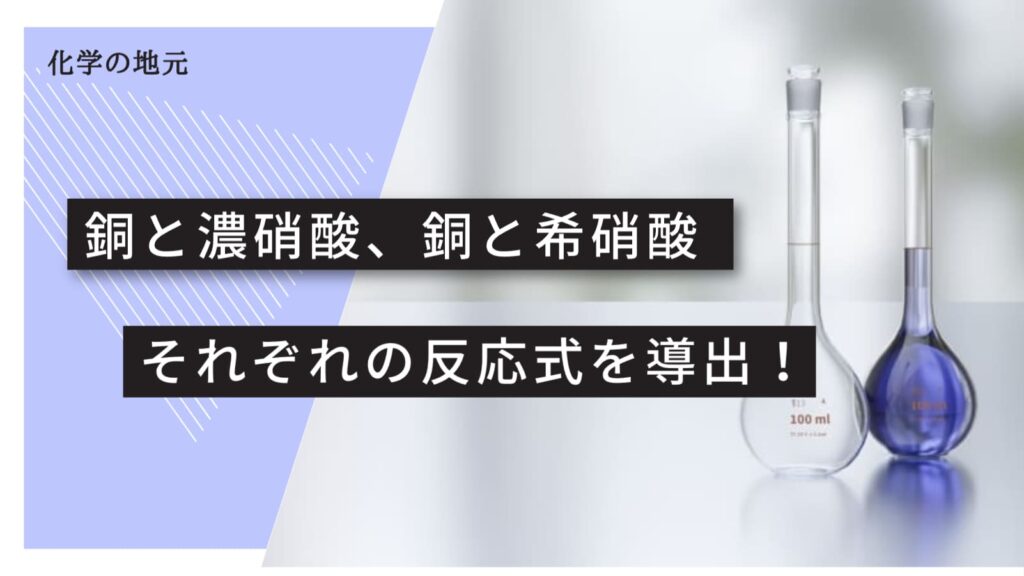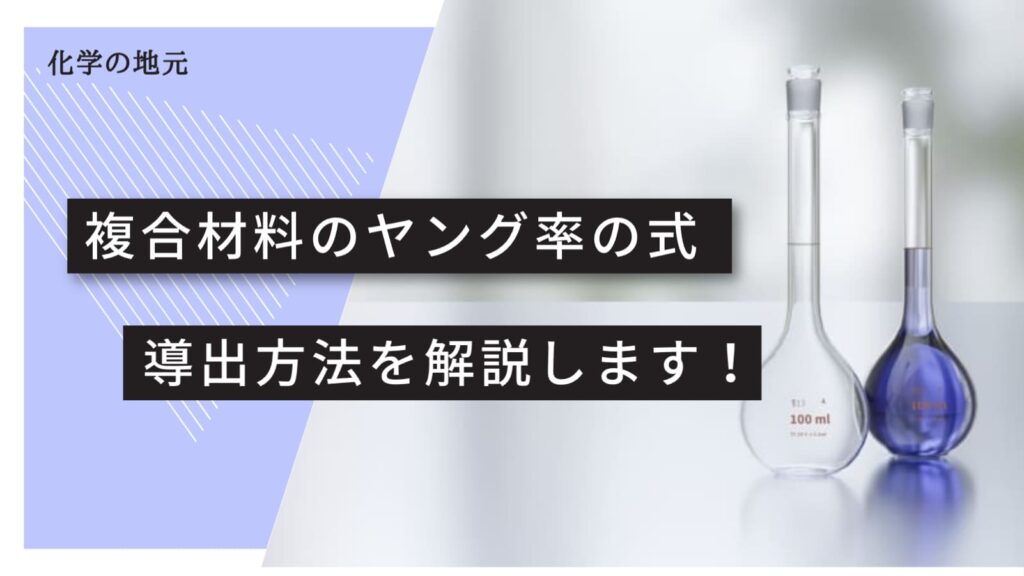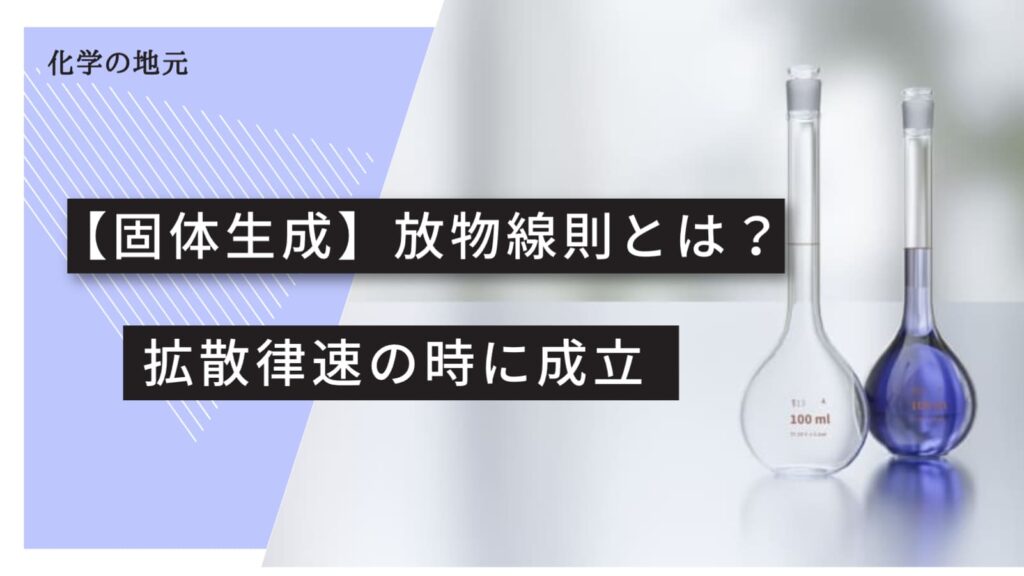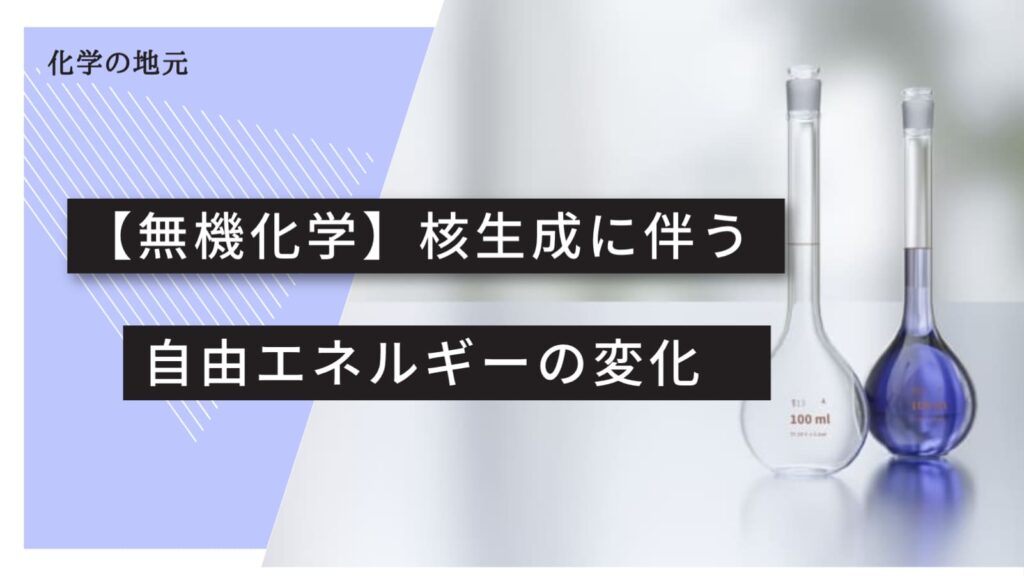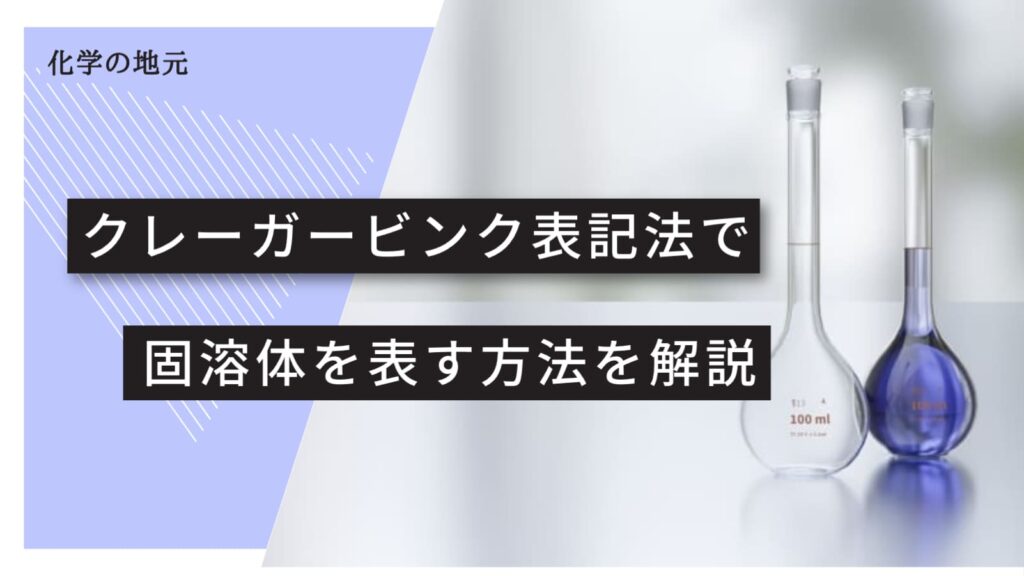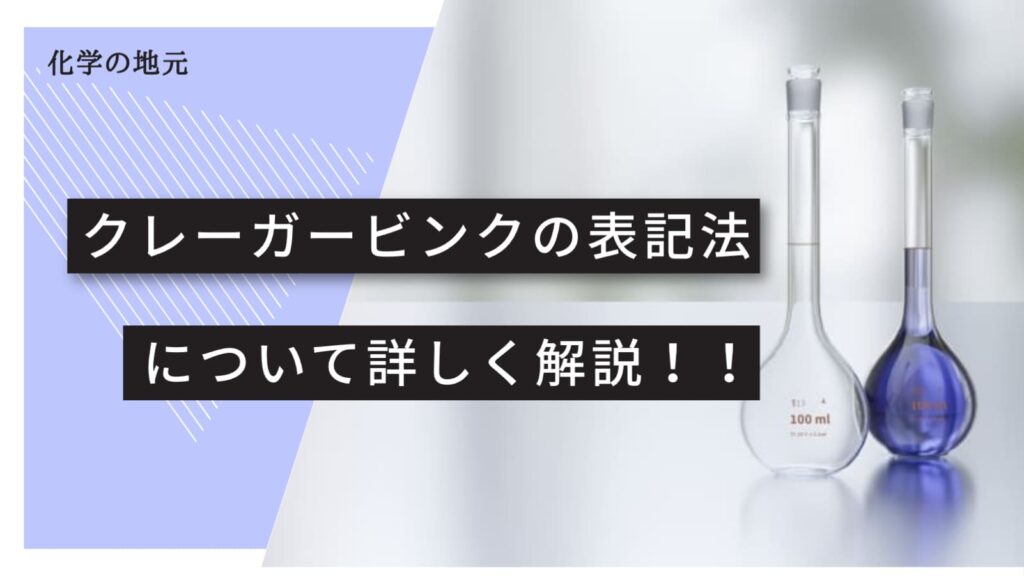無機化学– tag –
-

【化学】対称操作の「回反」と「らせん」を徹底解説!点群から空間群へ
化学の世界、特に分子の形や結晶構造を理解する上で、「対称性」という考え方は非常に重要です。対称性を数学的に記述するのが「対称操作」。その中でも、少し発展的な「回反 (かいはん)」と「らせん」について、この記事では徹底的に解説します。 この記... -

なぜp軌道の分子軌道はσ軌道が1つ、π軌道が2つになるのか?【図解でわかる軌道の重なり方】
化学の学習、特に分子軌道法(MO法)に進むと、「p軌道からできる分子軌道はσが1つとπが2つ」と習います。しかし、なぜ3つのp軌道がそのように分かれるのか、直感的に理解しにくいと感じる方も多いのではないでしょうか? この記事では、その理由をp軌道の... -

電池の種類と特徴を19種類まとめてみました
各種電池の反応と特徴 以下に、ご提示いただいた各種電池の正極反応と負極反応、そして特徴をまとめました。 1. ダニエル電池 正極反応: $\ce{Cu^{2+}(aq) + 2e^- -> Cu(s)}$ 負極反応: $\ce{Zn(s) -> Zn^{2+}(aq) + 2e^-}$ 特徴: 持続的に安定した電流を... -

【高校化学】気体発生のパターンを徹底解説
化学実験や試験問題では、特定の反応から気体が発生するパターンを理解することが重要です。本記事では、気体が発生する代表的なパターンと具体例をまとめます。 気体発生のパターン まず、気体発生のパターンを大まかに7つに分類します。 発生方法加熱の... -

銅と希硝酸、濃硝酸の反応の反応式の導出
銅(Cu)は酸化力の強い酸と反応しますが、酸の濃度によって反応が異なります。ここでは、希硝酸と濃硝酸の場合の化学反応式を導出する方法を説明します。 銅と希硝酸の反応 (1) 反応の概要 希硝酸(\(\ce{HNO3}\))は酸化力が弱いため、銅を溶かすには還... -

複合材料のヤング率の式の導出方法を解説!!
本記事では、複合材料のヤング率の求め方や影響因子について解説します。 1. 複合材料のヤング率の計算方法 複合材料のヤング率は、主に材料の配置(並列モデル・直列モデル)によって異なります。 基本的に2つのモデルのみを扱うので、以下で紹介する2... -

放物線則とは?【不均一系での固体生成】
放物線則とは、拡散に支配される成長プロセスにおいて、時間に対して成長厚さが放物線的(\(x∝tx \propto \sqrt{t}\))に増加することを示す経験則のことです。特に、高温酸化や固体中の拡散反応においてよく観察されます。 1. 放物線則の基本式 放物線則... -

核形成に伴う自由エネルギーの変化について解説!!【過冷却も】
相転移や結晶成長の初期段階では、新しい相(固相や液相など)の核が形成されます。このとき、系の自由エネルギーは体積エネルギーの減少と表面エネルギーの増加の影響を受けます。 これを表すのが、核形成に伴うギブス自由エネルギーの変化(ΔG)であり、... -

固溶体とクレーガービンクの表記法について解説
この記事では、固溶体をクレーガービンクの表記法で表すことについて解説します。 クレーガービンクの表記法がよくわからないという方は、以下の記事を一度見てみて下さい。 例①:ZrO2にCaOを添加したとき まず、ZrO2にCaOを添加したときを考えてみます。 ... -

クレーガービンクの表記法について詳しく解説!
クレーガービンクの表記法(Kräger-Vink notation)は、固体中の欠陥を表現するための記法です。 主に固体物理学や無機化学、材料科学などで使用され、結晶中の格子欠陥(空孔やドーパント原子など)を記述するのに使われます! クレーガービンクの表記法...